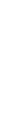体の司令塔である脳の視床下部働きと、自律神経の関係性とは?

「なんだか最近、寝ても疲れが取れない」
「些細なことでイライラしたり、胃腸の調子が不安定」
などの心と体の不調を一度は経験したことがある方も多いと思います。もしかすると、それは自律神経の乱れが原因かもしれません。そして、その自律神経をコントロールしているのが、脳の中心部にある視床下部というとても小さな部分です。
今回のコラムでは、ホルモンについて調べると必ず出てくる視床下部と自律神経の関係性についてお伝えしていきます。
視床下部とは何か?
視床下部は、脳のほぼ中央に位置する非常に小さな部分ですが、私たちの健康にとって“司令塔”のような存在です。体温調節、食欲、睡眠、感情、ホルモン分泌、自律神経のコントロールなど、生命維持に欠かせない多くの機能を管理しています。
特に、自律神経と女性ホルモンのバランスを司る中枢であることから、ストレスや生活習慣の乱れ、加齢などの影響を非常に受けやすい場所でもあります。
自律神経との関係性
視床下部は、交感神経と副交感神経という2つの自律神経のバランスを調整する中心的な役割を担っています。
たとえば、体が暑さを感じると視床下部が「体温を下げよう」と汗をかくよう指令を出し、寒さを感じると「体温を保とう」と血管を収縮させます。また、緊張やストレスを感じると心拍数や血圧を上げたり、リラックスした状態では胃腸を活発に動かすなど、その時々に応じた最適な状態へ導いてくれます。
つまり視床下部は、日々刻々と変化する環境や感情に対応して、体の内側のバランスを無意識のうちに整える働きをしてくれているのです。
女性ホルモンとの深いつながり
視床下部は、女性ホルモンの調整にも深く関わっています。
視床下部は、ホルモンの分泌を司る「下垂体」へ指令を出す役割を持っており、そこから卵巣へ働きかけ、エストロゲンやプロゲステロンの分泌を調整します。
このように、視床下部は「自律神経」と「ホルモン調整」の両方をコントロールしているため、一方が乱れると、もう一方も影響を受けやすくなるのです。
たとえば、ストレスや睡眠不足によって自律神経が乱れると、女性ホルモンの分泌も乱れやすくなり、生理不順やPMS、更年期症状の悪化といった不調が現れることもあります。逆に、ホルモンバランスが乱れると、それが引き金となって自律神経に影響し、イライラ、不眠、冷え、頭痛などの症状につながることも少なくありません。
ストレスが視床下部に与える影響
視床下部はとても繊細な部分であり、精神的ストレス・過労・睡眠不足・環境の変化といった影響に敏感に反応します。
ストレスが慢性化すると、視床下部の働きが低下し、自律神経やホルモンバランスの乱れが生じ、心身の不調が悪化しやすくなります。
たとえば、寝つきが悪くなったり、朝すっきり起きられない、食欲のコントロールがきかない、体温調整が苦手になる、などの症状が現れるのは、視床下部がうまく働いていないサインかもしれません。
カイロプラクティックとの関係性
カイロプラクティックでは、脊椎や骨盤での神経圧迫を取り除き、神経の流れをスムーズにし、脳と体の情報伝達の質を高めることを目指します。 視床下部の負担を減らし、自律神経やホルモンの乱れを根本から改善するサポートになります。
視床下部が適切に働くためには、脳からの指令が正確に体へ届く神経の通り道を整えることが大切です。 脳は体の情報に対して適切な判断をして、対処していきます。背骨や骨盤で神経の流れが阻害されてしまうと脳は体の状態をしっかり把握できない状態となります。
ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者中島 恵
新潟県東蒲原郡出身。柔道整復師資格取得後、2007年から2018年まで柔道整復師として接骨院勤務。その後、勤務地を横浜に変え整骨院で勤務。
シオカワスクールの哲学教室で塩川雅士D.C.からカイロプラクティックの自然哲学を学んだことや、塩川カイロプラクティックで実際の臨床現場を見学させていただいたことで、哲学・科学・芸術の重要性を知る。
現在は、前田カイロプラクティック藤沢院での診療を通じて地域社会の健康に寄与しながら、シオカワスクールでは女性初のインストラクターとして後任の育成にも力を入れている。
自分自身が女性特有の悩みで悩んでいた経験を活かし、誰にも相談できずにどこへ行っても改善されずに悩んでいる女性に寄り添えるようなカイロプラクターを目指している。