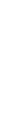PMS(月経前症候群)は肝臓のサイン?ホルモン代謝と自律神経の関係

「生理前になると気分が落ち込む」「体がむくむ」「胸が張って痛い」「頭痛や肌荒れが増える」——。
これらの症状はPMS(月経前症候群)と呼ばれ、多くの女性が経験しています。実はこのPMS(月経前症候群)、ホルモンのバランスだけでなく、肝臓の働きとも深く関係しているのをご存じでしょうか?
肝臓は“ホルモンの代謝工場”ともいえる臓器です。
今回は、PMS(月経前症候群)の背景にある肝臓の働きと、カイロプラクティックとの関係性についてお伝えしていきます。
■ PMS(月経前症候群)と女性ホルモンのリズム
PMS(月経前症候群)は、月経前にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)のバランスが急激に変化することで起こります。
排卵後、プロゲステロンが増えると体温が上がり、心身を落ち着かせる働きがありますが、同時にエストロゲンが過剰に残ると、体はむくみやすく、気分の浮き沈みも激しくなります。
つまり、PMS(月経前症候群)の多くは「エストロゲンがスムーズに代謝されず、体内に溜まっている状態」といえます。ここで重要な役割を果たすのが肝臓です。
■ 肝臓がホルモン代謝を担っている
肝臓は、体内で使い終わった女性ホルモンを分解し、排出しやすい形に変える働きをしています。
しかし、ストレスや睡眠不足、過労、薬の服用、アルコールの摂取などが続くと、肝臓が疲れてホルモン代謝の処理能力が落ちてしまいます。その結果、分解しきれなかったエストロゲンが体内に残り、PMS(月経前症候群)の症状が強く出ることがあります。
また、肝臓の機能が低下すると自律神経のバランスにも影響を及ぼし、イライラや不安感、集中力の低下といった精神的なPMS(月経前症候群)症状を悪化させることがあります。
つまり、PMS(月経前症候群)の背景には「ホルモンのアンバランス」だけでなく、「肝臓の疲労と自律神経の乱れ」が隠れているのです。
■ カイロプラクティックで肝臓と自律神経を整える
肝臓は右側の肋骨の下に位置し、背骨や横隔膜の動きと深く関係しています。自律神経が乱れることによって肝臓まわりの血流が悪くなり代謝機能が低下してしまいます。
カイロプラクティックでは、背骨や骨盤のバランスを整えることで、肝臓への血流や神経の働きを助け、体の内側からホルモン代謝を促すサポートを行います。
特にPMS(月経前症候群)の方は、自律神経の乱れが関係しているため、リラックスがうまくできない状態にもなりやすいです。体全体のホルモンバランスが安定することで肝臓の血流が回復しやすくなります。その結果、「生理前でも気持ちが落ち着くようになった」「むくみや胸の張りが軽くなった」といった変化を実感される方も多いです。
PMS(月経前症候群)は「ホルモンの問題」と考えられがちですが、その裏では肝臓の働きと自律神経のバランスが深く関わっています。肝臓を整えることはホルモンバランスを整える第一歩。
カイロプラクティック・ケアで体の土台を整え、PMS(月経前症候群)の不調を根本から軽減し、毎月のつらい症状を「仕方ない」と我慢せず、体の内側から見直していきましょう。
ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者中島 恵
新潟県東蒲原郡出身。柔道整復師資格取得後、2007年から2018年まで柔道整復師として接骨院勤務。その後、勤務地を横浜に変え整骨院で勤務。
シオカワスクールの哲学教室で塩川雅士D.C.からカイロプラクティックの自然哲学を学んだことや、塩川カイロプラクティックで実際の臨床現場を見学させていただいたことで、哲学・科学・芸術の重要性を知る。
現在は、前田カイロプラクティック藤沢院での診療を通じて地域社会の健康に寄与しながら、シオカワスクールでは女性初のインストラクターとして後任の育成にも力を入れている。
自分自身が女性特有の悩みで悩んでいた経験を活かし、誰にも相談できずにどこへ行っても改善されずに悩んでいる女性に寄り添えるようなカイロプラクターを目指している。