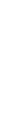症例紹介case introduction


何をしても改善しなかった末端冷え性に悩まされた毎日
末端冷え性が和らぎ元気に過ごせるようになりました!
カテゴリ:
循環器・泌尿器・内分泌器などの症状でお悩みの方
20代女性
- 来院に至った経緯
-
小学生から大学生まで長年にわたりダンスに取り組み、日常の一部として体を動かすことが当たり前の生活を送ってきた。
社会人になってからも、その習慣は続き、ピラティスやホットヨガに通いながら心身のバランスを整えていた。運動後の爽快感や汗をかいた後の充実感は、本人にとって欠かせない健康の源であった。
社会人3年目を迎える頃から状況は変わり始めた。責任ある仕事を任されるようになり、徐々に残業が増えていった。退社が遅くなればなるほど体を動かす時間は削られ、仕事中心の生活に傾いていった。
社会人5年目にはプロジェクトのリーダーを任され、緊張感のある日々が続いた。チームをまとめる立場としてのプレッシャーも大きく、帰宅は終電間際という日も珍しくなかった。その頃から、ふと「手足が異常に冷たい」と感じることが増え、「運動不足で血流が悪くなっているのだろう」と自己判断していた。
年末年始の休暇を利用して、久しぶりにピラティスやホットヨガに通った。体を動かすと気分が晴れ、体調も一時的には良いように感じられた。しかし、どれだけ汗をかいても、指先や足先の冷えは抜けなかった。
プロジェクトが一区切りして仕事量が落ち着いた後も、手足の冷えの症状は改善せず、むしろ「なぜ良くならないのか」という不安が大きくなっていった。
30歳を目前にしていたこともあり、「年齢のせいなのだろうか」「これがアラサーということなのか」と自分を納得させようとした。
この頃から、夜になると眠りが浅く、寝つきに時間がかかるようになり、途中で目が覚めてしまうことも増えた。
さらに午後になると頭痛を感じるようになり、パソコンに向かう時間は以前より減ったはずなのに「なぜか体調がすぐれない」と自覚するようになった。このような不調は「ただの冷え」だけではないのかもしれないと、漠然とした不安を抱くようになった。
健康意識の高い同僚に「最近、体調が悪くて手足が冷える」と相談したところ、「末端冷え性なら針治療がいいよ」と鍼灸院を紹介してもらった。
3か月ほど通院した結果、午後の頭痛は多少和らいだが、手足の冷えは依然として強く残り、冬場は外気に触れるとキンキンに冷たくなる状態が続いた。
鍼灸と並行してピラティスやホットヨガも再開し、定期的に体を動かす生活を取り戻したにもかかわらず、根本的な改善には至らなかった。
「これ以上どうすれば良いのだろう」と思い悩みながら方法を探していたときに、当院のホームページを目にする機会があった。
「手足の冷えの原因は自律神経にあるかもしれない」という記事を読み進めるうちに、自分が感じてきた不調の背景と重なっていると直感した。
これまでカイロプラクティックを受けた経験はなかったが、すみずみまでホームページを読み、「ここなら信頼できるかもしれない」という気持ちが芽生え、根本的な改善を期待して当院に来院された。
【神奈川県藤沢市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
左仙腸関節の明らかな可動域制限
- 02
左仙骨翼にスポンジ状の浮腫
- 03
頸部胸鎖乳突筋の過緊張
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、左の仙腸関節に明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、骨盤部と上部頸椎に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また左仙骨翼と第一頸椎左横突起に強い浮腫が確認され、腰部起立筋と頸部胸鎖乳突筋は過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中2段階のD2レベルで重度の骨盤の傾きや過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板の段階は6段階中2段階のD2レベルが確認され、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックとなっていた。
初期集中期の段階では週1回のケアから開始した。
3週目(3回目のアジャストメント)には、手足の冷えはまだ強く残っていたが、夜の寝つきが以前より少し早くなり、深く眠れる日が出てきた。午後に出ていた頭痛の頻度も軽減し始め、仕事終わりに「少し楽だ」と感じられる日が増えていった。
5週目(5回目のアジャストメント)には、冬場に特に強かった手足の冷えがやや和らぎ、外出時に冷たい空気に触れても以前ほどつらさを感じなくなった。睡眠についても途中で目が覚める回数が減り、朝まで眠れる日が増えてきた。この段階でケアのペースを2週間に一度に広げることができた。
11週目(8回目のアジャストメント)には、冷えを感じる時間帯が短くなり、特に午後の仕事中に手足が冷えて集中力が落ちるといった訴えがほとんどなくなった。相談していた同僚からも「最近、体調が良さそうだね」と声を掛けられるようになり、本人自身も客観的な変化を実感するようになった。
21週目(13回目のアジャストメント)には、冷え性の症状は大きく改善され、仕事や日常生活に支障を感じることはほとんどなくなった。以前は「これは年齢のせい」と思い込んでいたが、実際に体調が整っていくにつれて「本当に良くなってきている」と安心できるようになった。
現在は、ほとんどの症状が落ち着いているが、再発予防と身体のメンテナンスのために定期的なカイロプラクティックケアを継続している。
- 考察
-
今回の末端冷え性は、自律神経の乱れが主な原因であったと考えられる。検査において骨盤部および上部頸椎に顕著な反応が確認され、これらは副交感神経の働きに直結する重要な領域である。
副交感神経が十分に働けない状態では、交感神経の活動が優位となり、末梢血管を過度に収縮させてしまう。交感神経の作用そのものは生理的に必要なものであるが、その状態が慢性的に続くことで血流が滞り、手足などの末端に冷えを生じさせる。これは、長期的な過緊張状態が循環機能に与える典型的な影響のひとつである。
さらに今回のケースでは、冷えに加えて睡眠の質の低下や午後の頭痛もみられた。これらの症状も自律神経のアンバランスを裏づける所見といえる。
交感神経が過剰に働くと、夜間になっても心身が十分にリラックスできず、入眠困難や中途覚醒を引き起こしやすい。また、日中も常に交感神経が優位であるため筋緊張が持続し、午後に頭痛として症状が現れる。
緊張型頭痛の背景にはこのような神経学的メカニズムが存在しており、単なる疲労や姿勢の問題だけで説明できるものではない。
冷え性という症状は一見ありふれたものに思えるが、その原因は人によって大きく異なる。手足の末端だけが冷えるのか、下半身に限局しているのか、あるいは全身的に冷えているのか。
それぞれのパターンによって交感神経と副交感神経の関与の度合いや、代謝を司る甲状腺の影響を考慮する必要がある。甲状腺ホルモンは基礎代謝を左右するため、冷えやすさに直結する要因であり、自律神経との相互作用を無視することはできない。
したがって、冷え性の改善を考える際には「どの神経系が問題を起こしているのか」「どの椎骨レベルに異常があるのか」を正確に特定する検査力が不可欠である。
臨床においては、知識と検査力に加えて、問題となっている一つの椎骨に対して的確なアジャストメントを行う技術力が重要となる。神経系の乱れを見極め、その根本原因を取り除けるかどうかが、症状の改善に直結するからである。
アジャストメントによりサブラクセーション(根本原因)が取り除かれ、自律神経のバランスが整った結果、末端冷え性の改善だけでなく、睡眠の質や午後の頭痛といった随伴症状も大きく軽減したと考えられる。
今回のケースは、冷え性を単なる循環不良として捉えるのではなく、自律神経の働き全体を評価し、神経系の調整によって体が本来持つ回復力を引き出すことの重要性を示している。あらためて、神経の流れを整え、体の情報を正確に脳へ伝えることが健康維持に直結することを確認できた症例である。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。