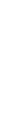症例紹介case introduction


長引く胃もたれで食事を楽しめなくなっていた毎日
胃もたれが解消し、安心して食事を楽しめるようになりました!
カテゴリ:
消化器・呼吸器・肌などの症状でお悩みの方
50代女性
- 来院に至った経緯
-
50代を迎えた頃から、これまで感じたことのないような「胃の重たさ」が食後に残るようになった。若い頃は友人や家族と外食をしても、多少食べ過ぎれば翌日にはすっきりと回復していた。しかしここ数年は、少量の食事でも「消化されないまま残っているような感覚」が続き、夕食後には特に強いもたれを感じるようになった。
最初のうちは「年齢のせいかな」「疲れているだけだろう」と軽く考え、市販の胃薬を服用してみた。飲んでいる間は多少症状が和らぐこともあったが、根本的な改善には至らず、薬をやめればすぐに元に戻ってしまった。食事の量を控えめにしたり、消化の良いものを選んだりと工夫を重ねたが、思うような効果は得られなかった。
そのうち「外で人と食事をするのがつらい」と感じるようになり、友人との会食や家族との外食も気が重くなった。せっかくの楽しい時間であっても、食後には胃が張って苦しくなることがわかっているため、心から食事を楽しめなくなっていた。
不安を感じて病院を受診し、内視鏡検査や血液検査を受けたが「特に異常はありません」と告げられた。整腸剤や胃薬を処方され、しばらくは服薬を続けたが、症状が完全に消えることはなかった。
「検査では異常なし」と言われながらも、実際には食べるたびに不快感がつきまとう現実に、どうすれば良いのか分からない苛立ちと不安を抱えていた。
近所で「胃腸の不調に良い」と評判の鍼灸院を見つけ、藁にもすがる思いで3か月間、週1回のペースで通ってみた。施術を受けるたびに一時的なリラックス感はあったものの、肝心の胃もたれそのものには変化がなく、期待が大きかった分、落胆も大きかった。
「やはり自分の体はこのまま改善しないのではないか」という諦めの気持ちが強まっていった。
症状が長引くにつれて、次第に体力や気力にも影響が及び始めた。食欲が落ち込み、食事の量が減ったことで体重も徐々に減少し、家族からは「もっと食べないと元気が出ないよ」と心配されるようになった。
しかし本人としては、食べたくても胃もたれの苦しさが先に立ち、思うように食べられないもどかしさが募っていた。
仕事や家事の疲労も重なり、夕方になると体がだるく集中力が続かない日も増えていった。症状そのものだけでなく、「このまま食べること自体が負担になってしまうのではないか」という不安が精神的にも大きな影響を及ぼし、気持ちまで沈むようになっていった。
そんなときに、当院のホームページを目にする機会があった。「胃の不調も自律神経の乱れと深く関わっている」という記事を読み進めるうちに、これまで原因が分からず悩み続けてきた自分の症状と重なる部分が多いと感じた。
「検査で異常がないと言われても、自律神経の問題なら説明がつくかもしれない」「ここなら根本的に向き合ってくれるのではないか」という期待を抱き、当院に来院された。
【神奈川県藤沢市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
第一頸椎左横突起にスポンジ状の浮腫
- 02
頸部左胸鎖乳突筋の過緊張
- 03
正中仙骨稜にスポンジ状の浮腫
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、第一頸椎には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、上部頸椎と骨盤部に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また第一頸椎左横突起と正中仙骨稜に強い浮腫が確認され、頸部胸鎖乳突筋は過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階はそれほど慢性的なところは確認されなかったが、仙骨の前傾が強く過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板の段階は6段階中4段階の慢性的なD4レベルが確認され、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックを通り越してスワンネック(逆カーブ)となっていた。
初期集中期の段階では週2回のケアを提示したが、平日は仕事の都合で予定が合わないことが多かったため、週1回のケアから開始した。
3週目(3回目のアジャストメント)には、食後の胃の張りが依然として残っていたものの、「以前よりも不快感が長引かなくなった」との変化を感じるようになった。夜に横になると苦しさが強まっていたが、その症状が少し軽減し、寝付きが改善し始めた。
6週目(5回目のアジャストメント)には、食後に「すぐ横になりたくなるほどの重たさ」は明らかに減少し、日中の活動に支障をきたすことが少なくなった。まだ胃もたれは時折出るものの、症状の強さは軽くなり、本人も「以前より食事が楽しめるようになった」と実感できていた。
11週目(9回目のアジャストメント)には、仕事中や家事の最中に感じていた全身のだるさが軽快し、夕方まで集中力が持続するようになった。これまでは胃の不快感で食欲が湧かず、少量しか食べられなかったが、食事の量も自然と増えてきた。家族からも「最近は元気そうに見える」と言われるようになり、体重の減少も止まって安定してきた。
19週目(14回目のアジャストメント)には、日常的な胃もたれの症状はほとんど感じなくなり、外食の機会にも安心して出掛けられるようになった。これまでは会食のたびに「後で苦しくなるのでは」と不安を抱えていたが、その心配が薄れ、気持ちの上でも余裕が戻ってきていた。
現在は、胃もたれの症状は落ち着き、体調も安定している。本人は「もう以前のように不調に振り回されることがなくなった」と語り、再発予防と健康維持のために定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
今回の胃もたれは、自律神経のアンバランスが主な原因であったと考えられる。食後の消化活動は、副交感神経が優位になることで円滑に進む。
副交感神経が十分に働くと胃酸の分泌が促進され、消化酵素の作用が高まり、胃の蠕動運動も活発になる。しかし、副交感神経の働きが低下すると胃酸の分泌量が不足し、食べ物が長時間胃に留まることで「胃の重さ」や「消化不良感」といった胃もたれの症状が現れる。
検査所見において上部頸椎と骨盤部に顕著な反応が認められた点は注目に値する。上部頸椎は迷走神経の走行と密接に関わっており、迷走神経は胃の運動・分泌の調整に不可欠な役割を果たしている。
一方、骨盤部は副交感神経系の仙髄領域に対応し、腸管全体の蠕動や排泄のリズムを支えている。これらの部位に問題が生じれば、副交感神経の活動が抑制され、消化機能が低下することは十分に説明可能である。
副交感神経が低下する一方で交感神経が優位に働くと、胃や腸の血流量が減少し、消化に必要なエネルギー供給が妨げられる。このような状態では「胃もたれ」という症状が繰り返し出現し、慢性的な不快感につながる。
つまり、胃そのものの器質的な異常がなくとも、自律神経のバランスが崩れれば十分に消化機能障害は起こり得るのである。
アジャストメントによってサブラクセーション(根本原因)が取り除かれた結果、迷走神経をはじめとする副交感神経の機能が正常化したことで、胃酸分泌と蠕動運動が回復し、血流も改善されたことで食後の胃もたれが解消されたと考えられる。
今回の症例は、胃もたれを単なる食べすぎや加齢の影響として片づけるのではなく、自律神経機能の評価と調整の重要性を示すものである。サブラクセーション(根本原因)を見極めて取り除くことで、胃腸の働きが本来の状態へと戻り、症状の改善につながることを再確認できた症例である。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。