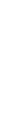症例紹介case introduction


薬を手放せない日々が続いた慢性的なじんましん
夜も眠れなかったかゆみが落ち着き、安心して過ごせるようになりました!
カテゴリ:
消化器・呼吸器・肌などの症状でお悩みの方
20代女性
- 来院に至った経緯
-
大学時代までは比較的健康で過ごしていたが、社会人になってから生活は一変した。食品メーカーに就職し、慣れない業務や人間関係のストレスに加え、残業や不規則な食生活が続くようになった。
食事は外食やコンビニに頼ることが増え、帰宅は深夜になることもしばしばであった。睡眠も浅く、疲労感が抜けないまま翌日を迎えることが多くなった。
そんな生活が続くうちに、半年ほど前から突然全身に赤いじんましんが出るようになった。特に夜になると腕や背中、太ももにまで広がり、かゆみで眠れない夜が増えていった。
朝起きても皮膚は赤く腫れ上がり、掻き壊した跡が残ってしまうこともあった。最初は「疲れているだけだろう」と思っていたが、症状は日に日に強くなり、鏡に映る自分の姿を見て落ち込むようになった。
皮膚科を受診すると「アレルギー反応でしょう」と説明を受け、抗ヒスタミン薬やステロイドの外用薬を処方された。薬を使うと一時的にかゆみや赤みは治まるが、数日経つと再びぶり返す。
その繰り返しに不安が募り、「一生薬を使い続けなければいけないのではないか」という恐怖を感じるようになった。
じんましんの症状は仕事や日常生活にも支障をきたしていた。人前に出る仕事柄、首や腕に赤い発疹が出ると周囲の視線が気になり、話すときにも自信を持てなくなった。かゆみで集中できず、作業効率も下がり、小さなミスを繰り返すことも増えた。
発疹が出ているときは外出や友人との予定を控えるようになり、「自分らしい生活ができなくなってしまった」と感じていた。
そんな中、同じ職場の先輩から「薬で抑えても根本は変わらないから、体の働きそのものを整える方法も考えてみたら?」とアドバイスを受けた。
その言葉をきっかけに、インターネットで「じんましん」「自律神経」「体質改善」といった言葉を調べていくうちに当院のホームページを見つけた。
そこには「慢性的な皮膚症状の背景には自律神経や免疫の働きの乱れが関わっている」という説明があり、薬ではなく体の根本にアプローチするという考え方に強く惹かれた。
「自分の症状ももしかしたら良くなるかもしれない」と初めて前向きな気持ちになれた。
薬に頼るのではなく、自分の体の力で症状を改善したいという思いから、「本当に根本から変わりたい」という決意を持って当院に来院された。
【神奈川県横浜市戸塚区から来院】
- 初診の状態
-
- 01
左仙腸関節の明らかな可動域制限
- 02
左仙骨翼にスポンジ状の浮腫
- 03
第一頸椎左横突起にスポンジ状の浮腫
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、左の仙腸関節には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、骨盤部と上部頸椎に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また左仙骨翼と第一頸椎左横突起に強い浮腫が確認され、腰部起立筋と頸部胸鎖乳突筋は過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中3段階の慢性的なD3レベルで重度の骨盤の傾きや過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板はそれほど慢性的な段階は確認されなかったが、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックを通り越してスワンネック(逆カーブ)となっていた。
初期集中期の段階では週2回のケアを提示したが、仕事が多忙で平日は残業も多く都合が合わなかったため、週1回のケアから開始した。
3週目(3回目のアジャストメント)には、依然として夜になると腕や背中に発疹が出ることが多かったが、以前のように一晩中強いかゆみで眠れないという日は減り始めていた。本人も「少しは眠れるようになった」と話すようになり、初期段階としては小さな変化が見られた。
7週目(6回目のアジャストメント)には、肌に出るじんましんの範囲が狭まり、症状の出ない日が週の半分ほどになった。かゆみも以前ほど強烈ではなくなり、薬を使う頻度が少しずつ減ってきた。仕事でも「かゆみで集中できない」という場面が減少し、日常生活における負担が軽くなりつつあった。この段階でケアのペースを2週間に1回へと広げることができた。
12週目(9回目のアジャストメント)には、夜間に強く出ていたじんましんがほとんど出なくなり、眠れる日が安定して増えていった。日中に発疹が出ても軽度で、数時間のうちに自然に引くようになり、本人も「薬に頼らなくても落ち着くことが増えてきた」と自信を持てるようになっていた。
20週目(13回目のアジャストメント)には、慢性的に続いていた発疹はほとんど気にならなくなり、皮膚の赤みやかゆみも大幅に減少していた。以前は外見が気になって外出を避けていたが、友人との予定を楽しめるようになり、仕事にも前向きに取り組めるようになった。
現在は、じんましんの症状はほとんど落ち着いているが、生活のストレスや季節の変化で再び悪化しないように、体のメンテナンスとして定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
今回のじんましんは、自律神経、特に交感神経の過剰な働きが原因であったと考えられる。
一般的にじんましんは、皮膚に存在する肥満細胞からヒスタミンが放出されることで起こる。ヒスタミンは血管を拡張させたり透過性を高めたりするため、皮膚に赤みや膨疹を生じさせる。
さらに知覚神経を刺激してかゆみを引き起こす。このヒスタミン放出のきっかけとしては、特定の食物や薬剤、物理的刺激、感染、あるいはストレスが知られているが、慢性じんましんの多くは原因不明とされている。
ここで注目すべきは、ヒスタミンの分泌と交感神経の関わりである。交感神経が過剰に優位になると、顆粒球の比率が上昇し、その中でも特にアレルギー反応に深く関与する好塩基球が増える。
好塩基球はアレルゲンやストレスの刺激を受けると活性化し、大量のヒスタミンを放出する。するとヒスタミンが知覚神経を刺激し、かゆみを生じさせると同時に、さらに神経ペプチドを介して肥満細胞を刺激し、さらなるヒスタミン分泌を招く。
この悪循環が続くことで、慢性的なじんましんの症状が現れていたと考えられる。
検査では、骨盤部や上部頸椎に強い反応が確認された。これらの部位は副交感神経支配の領域と深く関わる部位となる。この領域での神経圧迫が交感神経を過剰に興奮させていた可能性が高い。
その結果、ヒスタミン分泌の制御が効かなくなり、じんましんの発症と慢性化を助長していたのだろう。
アジャストメントによってサブラクセーション(根本原因)が取り除かれたことで、副交感神経の機能によって交感神経の過剰な興奮が抑えられ、自律神経のバランスが回復した。その結果、好塩基球や肥満細胞からのヒスタミン放出が落ち着き、かゆみや発疹といった症状が改善に向かったと推察される。
今回の症例は、じんましんを単なる皮膚症状として捉えるのではなく、自律神経と免疫機能の連動という観点から考える重要性を示している。
神経の働きを整えることによって、体内で繰り返されるヒスタミン分泌の悪循環を断ち切り、本来の安定した状態へ導くことができることを再確認できた症例であった。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。