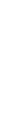症例紹介case introduction


腱鞘炎でヴァイオリンが弾けない恐怖に苦しんだ音大生の手首の痛み
痛みを気にせず演奏に集中できるようになり、舞台で音楽を心から楽しめるようになりました!
カテゴリ:
外傷・スポーツ外傷・上肢下肢の症状でお悩みの方
20代女性
- 来院に至った経緯
-
幼い頃から音楽に親しみ、ヴァイオリンは人生の一部ともいえる存在であった。小学生の頃にはすでに音楽教室で頭角を現し、練習時間も人一倍多く、将来は音楽の道に進むことを自然と志していた。大学では音楽を専門的に学び、日々の生活の中心はヴァイオリンといっても過言ではなかった。
しかし、長時間の練習を重ねる中で、右手首に違和感を覚えるようになった。最初は「疲れが溜まっているだけだろう」と思い、無理を押して弓を握り続けたが、痛みは次第に強くなっていった。特に速いパッセージや力強い弓使いを必要とする曲では、手首の奥に鋭い痛みが走り、思うように音が出せなくなった。
痛みを抱えながらの演奏は、彼女にとって大きなストレスとなった。舞台の上では常に「また手首が痛むのではないか」という不安がつきまとい、演奏に集中できなくなっていった。実際、音楽コンクールの本番でも、緊張と痛みが重なり、思い描いていた表現ができず、悔し涙を流した経験もあった。
整形外科を受診すると「腱鞘炎」と言われ、湿布や痛み止めで様子をみるよう指導された。しかし、症状は一時的に和らぐものの、練習を再開するとすぐに痛みがぶり返してしまった。周囲からは「練習を減らせばいい」と助言されたが、コンクールや授業のために練習量を減らすことは現実的ではなかった。
「このままでは演奏家としての道を閉ざされてしまうのではないか」という恐怖が日に日に大きくなり、音楽そのものを楽しめなくなっていった。大切な舞台で力を出し切れない自分を責め、ヴァイオリンを手に取ることすら怖く感じる瞬間もあった。
そんなとき、同じ音大の先輩が「うちの母親はここに行って手首の腱鞘炎が治ったから、そんなに困っているなら行ってみたら」と当院の存在を教えてくれた。信頼できる先輩の言葉に背中を押され、「大好きなヴァイオリンを思い切り弾きたい」という切実な思いから、当院に来院された。
【神奈川県鎌倉市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
下部頸椎の明らかな可動域制限
- 02
隆椎周辺の強い浮腫感
- 03
頸部から肩にかけての過緊張
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、下部頸椎には明らかな可動域制限があった。体表温度検査でも、下部頸椎に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また隆椎周辺に強い浮腫が確認され、頸部から肩にかけては過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中2段階のD2レベルで反り腰が確認された。首の椎間板の段階は6段階中3段階の慢性的なD3レベルが確認され、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックとなっていた。
初期集中期の段階では週2回のケアを提示したが、音大の授業や練習時間を確保したいとのことで、週1回のケアから開始した。
2週目(2回目のアジャストメント)には、弓を持つ際の手首の鋭い痛みが和らぎ、「以前のように力まずに音が出る感覚が少し戻ってきた」と本人が語った。練習後の疲労感は依然として残ったものの、翌日のこわばりは軽減していた。
5週目(5回目のアジャストメント)には、長時間の基礎練習をしても痛みが強くぶり返すことが少なくなった。特に細かいフレーズを繰り返す際、以前は手首の奥に鋭い痛みが走っていたが、この頃には「張るような感覚はあるものの、演奏を中断するほどではない」と語り、コンクールに向けた練習を安心して続けられるようになった。この段階でケアのペースを2週間に一度に広げることができた。
9週目(7回目のアジャストメント)には、手首の可動性が改善し、弓のコントロールがしやすくなった。本人も「音が以前より伸びやかに響くようになった」と演奏面での変化を実感していた。また、授業でのアンサンブル演奏でも痛みを気にせず集中できるようになり、表現力にも余裕が出てきた。
15週目(10回目のアジャストメント)には、強いビブラートや速いパッセージでも痛みを感じなくなり、音楽表現に対する不安が解消された。舞台に立つ際の恐怖心も消え、「ようやく演奏を楽しめるようになった」と笑顔で話していた。
現在は、手首の痛みは完全に落ち着き、大好きなヴァイオリンを存分に弾けるまでに回復したが、「再び痛みで演奏が制限されるのは避けたい」との思いから、身体のメンテナンスとして定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
今回の右手首の痛みは、表面的には腱鞘や靭帯への繰り返しの負担による、いわゆる「腱鞘炎」として現れていたが、その背景には首から手首に向かって伸びる神経機能の低下が深く関与していたと考えられる。
頸椎から分岐する神経は上肢全体を支配しており、特に下部頸椎の不安定性は手首や指の運動機能や感覚に直結する。首の働きが乱れると末梢への神経伝達が滞り、手首における循環不全や筋緊張を助長し、局所の炎症を慢性化させる要因となる。
手首は橈骨・尺骨に連結する8個の手根骨によって構成され、それぞれが数ミリ単位の微細な動きを連動させることで全体の安定性と柔軟性を維持している。ヴァイオリン演奏では、長時間にわたり一定の姿勢で弓を操作し続けるため、こうした微細な動きが繰り返し酷使される。
もし首の機能低下により神経の働きが阻害されれば、手根骨の連動性が失われ、特定の関節や腱に過剰な負担が集中しやすくなる。今回の症例では、まさにその結果として痛みが固定化し、演奏を妨げるほどの支障となっていたと考えられる。
注目すべきは、局所に湿布や痛み止めを用いても改善が一時的であった点である。これは炎症そのものが原因ではなく、「なぜ炎症が繰り返し起こるのか」という根本的な問題にアプローチできていなかったことを示している。
実際に首の機能を改善するアジャストメントを行ったことで、神経伝達が正常化し、手首の筋緊張が緩和された。その結果、演奏中の細かな弓さばきや速いパッセージでも痛みが再発せず、むしろ演奏の表現力や音の伸びやかさに良い影響をもたらしたことは特筆すべきである。
音楽家にとって手首の問題は職業生命に直結する重大な課題であるが、その解決には局所だけでなく全身の神経学的評価が不可欠である。今回の症例は、カイロプラクティックが単なる痛みの緩和にとどまらず、演奏者のパフォーマンスを根本から支える臨床的意義を示している。そして最終的に首のサブラクセーション(根本原因)を正確に取り除くことが、身体本来の治癒力と機能回復を引き出す鍵となった。
この症例が示唆するのは「職業や趣味で繰り返し同じ動作を行う人々」に共通するリスクである。楽器演奏に限らず、パソコン作業やデスクワーク、スポーツなど、現代人の多くは知らず知らずのうちに同じ関節や筋肉に偏った負荷をかけ続けている。
その結果、局所の炎症や痛みを繰り返し、最終的に慢性化してしまうケースは少なくない。つまり、このヴァイオリン奏者の回復は、特殊な例ではなく「誰にでも起こり得る問題」であり、その解決には神経と全身のつながりを重視するアプローチが不可欠であることを改めて証明している。
本症例は音楽家としてのキャリアを左右する深刻な手首の痛みに対して、神経学的な視点から根本原因にアプローチすることで演奏活動を再び可能にした臨床的に重要な症例であった。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。