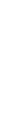症例紹介case introduction


授業も部活動も続けられない強烈な眠気に苦しんだ中学生のナルコレプシー
授業もサッカーも最後までやり遂げられるようになり、笑顔が戻りました!
カテゴリ:
子供の健康でお悩みの方
10代男性
- 来院に至った経緯
-
小学生の頃から授業中に居眠りをして先生に注意されることがあったが、周囲からは「夜更かししているからだろう」「勉強に集中できていないだけ」と片付けられていた。本人も「自分がだらしないのかもしれない」と思い込み、特に気にせず過ごしていた。
ところが中学2年生になった頃から状況は一変した。授業が始まってしばらくすると、急に強烈な眠気が襲ってきて、そのまま意識が途切れるように机に突っ伏してしまうことが何度も起こった。
周囲からは「やる気がない」「怠けている」と誤解され、クラスメイトの視線が気になるようになった。友人との会話中でも、笑っていたはずなのに気づけば眠ってしまっていることがあり、「変だ」と言われるたびに胸が締め付けられるような思いをしていた。
部活動はサッカーをしていたが、そこでも影響は大きかった。練習の最中や試合の直前に強い眠気が来て動けなくなり、監督からは「集中力が足りない」と叱責されることもあった。仲間と一緒に頑張りたいのに、自分だけが取り残されることへの悔しさと、どうしようもできない身体への苛立ちで、次第に活動への意欲も失われていった。
両親はそんな息子を見て「まだ中学生なのに、どうしてこんなに疲れてしまうのか」「もしかしたら大きな病気なのでは」と強い不安を覚え、病院に相談した。睡眠検査を受けた結果、「ナルコレプシーの可能性がある」と告げられ、薬による治療を勧められた。
しかし薬を使うことに抵抗があり、家族としても「一生薬を飲み続けなければならないのか」という不安が拭えなかった。
母親は「なんとか根本的に良くする方法はないのか」とインターネットで必死に情報を探すようになった。その中で、「自律神経と睡眠障害の関係」に触れた記事を目にし、さらに検索を進めるうちに当院のホームページに辿り着いた。
そこには、同じように睡眠の問題で悩んでいた人の症例が紹介されており、「根本的に神経の働きを整えることで眠気に変化が出るかもしれない」と強い希望を抱いた。母親の後押しと本人の「このままでは学校生活も部活も続けられない」という切実な思いが重なり、家族とともに当院へ来院された。
【神奈川県藤沢市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
左上後腸骨棘上端にくぼんだ浮腫
- 02
左仙腸関節の可動域制限
- 03
第一頸椎左横突起にスポンジ状の浮腫
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、左の仙腸関節には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、骨盤部と上部頸椎に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また左上後腸骨棘上端と第一頸椎左横突起に強い浮腫が確認され、腰部起立筋と頸部胸鎖乳突筋は過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中D3段階の慢性的なD3レベルで重度の骨盤の傾きや過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板の段階はそれほど慢性的なところは確認されなかったが、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックを通り越してスワンネック(逆カーブ)となっていた。
患者は中学2年生であったが、授業中はおろか部活動中でも眠気に襲われるという状態だったため、初期集中期の段階では週1回のケアから開始した。
3週目(3回目のアジャストメント)には、授業中に強い眠気が起こる回数がわずかに減り、本人も「少し授業を最後まで聞ける日がある」と口にするようになった。依然として眠気は残っていたが、小さな変化に本人も家族も希望を感じていた。
7週目(6回目のアジャストメント)には、昼休みの後に必ず眠ってしまっていたのが、短時間の居眠りで済むようになった。部活動でも「途中で意識が飛ぶ」ような状態は減り、監督や仲間からも「最近は集中できているね」と声をかけられる場面が出てきた。この段階でケアのペースを2週間に一度に広げることができた。
13週目(9回目のアジャストメント)には、授業中に眠気を我慢できずに寝込んでしまうことは大幅に減り、生活リズムが安定してきた。本人は「まだ眠くなることはあるけれど、起きていられる時間が増えた」と話し、以前のように自分を責める気持ちは和らいでいた。
21週目(13回目のアジャストメント)には、授業や部活動を最後までやり遂げられる日が増え、担任の先生からも「表情が明るくなった」と評価されるようになった。家族も「以前のように笑顔で会話する時間が戻ってきた」と安心し、本人の学校生活への自信も回復しつつあった。
現在は、強い眠気による中断はほとんどなくなり、日常生活や学校生活を大きな支障なく送れている。再発防止と身体のメンテナンスのために、定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
今回のナルコレプシーは、脳内の覚醒を維持する役割を持つ神経伝達物質「オレキシン」の分泌低下が背景にあったと考えられる。オレキシンの不足は、自己免疫的な機序や感染症、慢性的なストレスなどが要因として報告されており、これらはいずれも自律神経の乱れと密接に関わっている。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、そのバランスは免疫系の働きに大きく影響を与える。交感神経が優位になると白血球の中で顆粒球の比率が増加し、炎症や組織破壊が進みやすくなる。
一方、副交感神経が優位になるとリンパ球の比率が高まり、免疫の制御や回復の働きが強まる。顆粒球とリンパ球の比率が大きく崩れると、感染症への抵抗力低下や自己免疫的な過剰反応が誘発され、神経伝達物質の異常や神経細胞の機能障害を引き起こすことになる。
本症例における検査では、骨盤部と上部頸椎に強い反応が確認された。いずれも副交感神経の支配と深く関連する領域であり、副交感神経の機能低下によって交感神経が過剰に優位になった結果、自律神経の恒常性が大きく乱れていたと推測される。
交感神経の過緊張が続くと、免疫のバランスは崩れ、オレキシン産生系にも影響が及び、覚醒維持機能の低下につながっていたと考えられる。
カイロプラクティックケアにより上部頸椎や骨盤部のサブラクセーション(根本原因)を取り除くことで、副交感神経の働きが回復し、自律神経全体のバランスが整っていったと考えられる。その結果、免疫機能の過剰反応が抑制され、脳内の神経伝達環境が改善に向かい、ナルコレプシー症状が軽減したと推測される。
この症例は、ナルコレプシーの改善が単に脳内物質の問題にとどまらず、自律神経・免疫・神経伝達の三者が複雑に連動していることを示している。サブラクセーションという根本原因にアプローチするカイロプラクティックの意義を明確に示す症例であった。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。