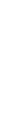症例紹介case introduction


投げるたびに走る右肘の痛みで全力投球ができなかった高校野球生活
長年苦しんだ右肘の痛みが軽減し、安心してマウンドに立てるようになりました!
カテゴリ:
外傷・スポーツ外傷・上肢下肢の症状でお悩みの方
10代男性
- 来院に至った経緯
-
小学生の頃からリトルリーグで野球を始め、中学ではリトルシニアで活躍し、高校は甲子園を狙える強豪校に進学した。投手としてチームの中心を担い、プロを夢見て日々練習に励んできた。
しかし、高校2年の春頃から右肘に違和感が出るようになった。最初は「疲労が溜まっているだけ」と考えていたが、投げるたびに痛みは強まり、全力投球が難しくなっていった。整形外科を受診すると「骨には異常なし。成長期の影響もあるから、しばらく安静にしていれば良くなるでしょう」と説明された。
だが、最後の大会が迫る中で「安静にしていれば良い」と言われても現実的には難しく、焦りと不安ばかりが募っていった。両親が評判の接骨院や整体院を探してくれて通ってみたが、その場では多少軽くなる程度で、練習に戻ると痛みはすぐにぶり返した。
「このままでは最後の大会に間に合わないのではないか」「投手として続けられなくなるのではないか」という不安が頭を離れず、精神的にも追い込まれていった。結局、高校3年の最後の大会も満足に投げることができず、悔しさを抱えたまま敗退。全力を出せないまま高校野球が幕を閉じた。
大学に進学して野球は続けたが、右肘の痛みは完全には消えず、練習でも試合でも思い切り投げられないもどかしさが続いた。仲間が伸びていく中、自分だけが本来の力を発揮できない現実に焦りを感じ、苛立ちや不安で心身ともに追い詰められていった。
そんな息子を間近で見ていた両親は「このままでは潰れてしまう」と強い危機感を覚え、何か方法はないかと情報を探し続けていた。その中で当院のホームページを見つけ、「肘の痛みは局所だけでなく、神経の働きや全身のバランスとも深く関わっている」という記事を目にした。
「今までのように肘だけに注目していては根本的な改善にならないのではないか。全身のバランスを見直してもらった方が良いのではないか」と両親から提案を受け、本人も「全力で投げられるようになるなら、なんでも試してみたい」と希望を抱き、当院に来院された。
【神奈川県横浜市西区から来院】
- 初診の状態
-
- 01
隆椎周辺の強い浮腫感
- 02
背部から腰部にかけての脊柱起立筋の過緊張
- 03
右仙腸関節の明らかな可動域制限
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、右の仙腸関節と下部頸椎には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、下部頸椎と中部胸椎、骨盤部に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また隆椎周辺と右上後腸骨棘上端内縁に強い浮腫が確認され、背部から腰部にかけての脊柱起立筋は過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中3段階の慢性的なD3レベルで重度の骨盤の傾きや過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板の段階も6段階中3段階の慢性的なD3レベルが確認され、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックとなっていた。
長年の体の酷使の影響か頸部や腰部に炎症反応も見れらたため、初期集中期の段階では週2回のケアから開始した。
3週目(4回目のアジャストメント)には、肘を動かす際の鋭い痛みが和らぎ、キャッチボール程度であれば支障なく行える場面が増えてきた。投球後の重だるさも徐々に引きが早くなり、練習への復帰に対する不安がいくぶん軽減してきた。
7週目(10回目のアジャストメント)には、練習量を増やしても痛みの戻りが小さくなり、投球フォームに安定感が出てきた。以前は無意識にかばってフォームが崩れやすかったが、体の軸が安定することで投球動作がスムーズになったと実感するようになった。この段階でケアのペースを1週間に一度に広げることができた。
12週目(15回目のアジャストメント)には、練習量を増やしても肘の痛みが大きくぶり返すことは少なくなり、試合での登板機会も増えていった。多くの球数を投げた試合のあとには肘の内側に張りを感じることもあったが、以前のように数日間痛みが続くことはなく、翌日には違和感が軽減するようになっていた。そのため投球フォームをかばう必要がなくなり、体の軸が安定することで全身を使ったスムーズな投球動作が可能となっていった。
17週目(20回目のアジャストメント)には、大学野球で初めて公式戦の先発マウンドを任され、1回から7回まで全力で投げ切ることができた。これまでのように右肘に強い痛みが出ることはなく、試合後も炎症や張りは最小限に留まり、翌日には違和感なく練習に復帰できるほど回復もスムーズであった。
現在は、右肘の痛みはほとんど解消し、投球動作にも不安を感じることがなくなった。再発を防ぐだけでなく、試合で最高のパフォーマンスを発揮するために、定期的なカイロプラクティックケアを継続している。
- 考察
-
今回の右肘の痛みは、直接的には尺骨神経への負担が原因であったと考えられる。投球動作を繰り返すことで局所的に神経が圧迫され、炎症や違和感として痛みが顕在化していた。
しかし、その背景には全身的な構造の乱れが存在していた。検査では骨盤部の不安定性に加え、中部胸椎に明らかな可動制限が確認された。この制限は肩甲骨の動きに影響し、右肩から右肘に至るまでの動作連鎖に制約を与えていた。
つまり、骨盤部の乱れが背骨を通じて中部胸椎へ波及し、さらに肩甲帯から上肢全体へと負担を広げていたのである。
特に投球動作では、骨盤から胸郭、肩甲骨、上腕骨、そして前腕・肘へとエネルギーが順に伝達される。このように体の複数の関節や筋肉が連動しながらひとつの動作を生み出す仕組みは「運動連鎖(キネティックチェーン)」と呼ばれる。
投球はまさにこの運動連鎖の典型であり、どこか一部の動きが制限されると、その負担は末端にまで跳ね返る。骨盤や胸椎の可動性が失われると、肩甲骨の外転や上方回旋が制限され、結果的に肩関節に過剰なストレスが集中する。
その負荷はさらに肘関節に波及し、尺骨神経周囲の組織に繰り返し摩擦や牽引ストレスを与えていたと考えられる。
そして何よりも重要なのは、頸部から右腕にかけて伸びる神経経路への過剰な負荷である。骨盤部と中部胸椎の問題によって全身のバランスが崩れた結果、頸椎レベルで腕神経叢にかかるストレスが増大し、尺骨神経に負担が集中していたと推察される。
反復投球に伴う微細な外傷は、局所の安静だけでは改善されにくく、全身の構造的連動性を取り戻すことが必要不可欠である。
アジャストメントによって骨盤部や中部胸椎の機能を回復させることで、全身の運動連鎖が整い、頸部から右上肢にかけて伸びる神経にかかる不均衡な負荷も解消された結果、尺骨神経が正常に働ける環境が回復し、右肘の痛みが改善に至ったと考えられる。
今回の症例は、肘の痛みを単なる局所のオーバーユースとして片づけるのではなく、全身の構造と神経機能の連動性を考慮した評価の重要性を示している。
サブラクセーション(根本原因)を見極め、全身のバランスを整えることで、局所の神経負担が解消され、本来の投球パフォーマンスを取り戻すことができることを再確認できた症例である。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。