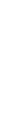症例紹介case introduction


何度も繰り返す足首の捻挫で全力で走れなくなったサッカー選手
再びフィールドで思い切りプレーできるようになりました!
カテゴリ:
外傷・スポーツ外傷・上肢下肢の症状でお悩みの方
20代男性
- 来院に至った経緯
-
3人兄弟の末っ子として育ち、幼い頃から兄2人の影響でサッカーに夢中になっていた。兄たちはいずれも地域のクラブチームで活躍しており、放課後はいつも一緒にボールを蹴って過ごした。小学生のときから兄たちに混ざって練習をするのが日課で、周囲の大人たちからも「センスがある」と言われるほどサッカーが好きだった。
小学3年生でクラブチームに入ってからは、練習量も一気に増えたが、その頃から右足首の捻挫を繰り返すようになった。軽いものなら数日休めば回復したが、数か月に一度は腫れが強く、松葉杖を使うほどの重度の捻挫も経験した。整形外科では「靭帯が伸びていて関節が緩みやすい」「リハビリを続けて筋肉で支えるしかない」と説明を受けたが、根本的な改善には至らなかった。
中学・高校と進むにつれて、競技レベルが上がる一方で、足首への不安は常に付きまとった。高校では全国大会を目指す強豪校に進学し、フォワードとしてチームの中心的存在だったが、シーズンを通して痛みや違和感が消えることはなかった。大会を目前にして再び捻挫し、重要な試合を欠場したときには、悔しさと無力感で涙が止まらなかった。
高校卒業後も、大学や社会人チームでサッカーを続けてきた。ポジションは変わらずフォワード。社会人になっても休日はグラウンドに立ち、仕事のストレスをサッカーで発散するのが生きがいだった。しかし20代半ばを過ぎた頃から、練習中や試合中に何でもない場面で足首をひねることが増えた。以前なら数日で治っていた痛みが、今回はいつまでも引かず、走るたびに足首のぐらつきを感じるようになった。
整形外科に行っても「靭帯がゆるくなっているからリハビリして」としか言われなかった。電気治療やリハビリを続けても感覚的な不安は解消されず、テーピングをしても安心してプレーできない。何よりも「もう全力で走れないかもしれない」という恐怖が、サッカーに対する情熱を少しずつ奪っていった。
そんな中、同じチームの仲間から「自分は膝だったけど、ここで骨盤整えてもらったら膝の痛み出なくなったから、一度行ってみたら?」と当院を紹介してもらった。
半信半疑で当院のホームページを調べてみると、「根本改善」という言葉がやたらと目につき、「長年の捻挫癖にも根本原因があるのか」と思い、当院に来院された。
【神奈川県平塚市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
右仙腸関節の明らかな可動域制限
- 02
右上後腸骨棘上端内縁の強い浮腫感
- 03
脚長差右短下肢2㎝
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、右の仙腸関節には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、骨盤部に明らかに左右の温度の誤差が確認され、右上後腸骨棘上端内縁に強い浮腫が確認された。腰部起立筋は過緊張の状態で、脚長差は右短下肢で2㎝も右脚が短くなっていた。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中4段階の慢性的なD4レベルで重度の骨盤の傾きや過前弯で反り腰が確認された。首の椎間板の段階はそれほど慢性的なところは確認されなかったが、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックとなっていた。
初期集中期の段階では週2回のケアを提示したが、平日は残業も多く時間的に難しいとのことだったので、無理のない範囲で週末の週1回のケアから開始した。
2週目(2回目のアジャストメント)には、立位での安定感が少しずつ改善し、仕事中の長時間立位でも右足首の違和感が軽減した。アジャストメント後の歩行では、足裏の接地感が均等になり、本人も「右足にしっかり体重が乗る感じがある」と話していた。
4週目(4回目のアジャストメント)には、サッカーの練習中も足首のぐらつきをほとんど感じなくなった。試合中に軽い接触を受けても捻る恐怖感がなく、関節の安定性が増していることを実感していた。この段階でケアのペースを2週間に一度に広げることができた。
10週目(7回目のアジャストメント)には、右ふくらはぎの慢性的な張りが取れ、足首の可動域も拡大した。蹴り動作時のフォームが安定し、キック力と精度が向上。本人は「以前よりボールをミートしやすい」と話しており、動作の連動性が明らかに改善していた。
18週目(11回目のアジャストメント)には、試合後の疲労感も軽くなり、連戦でも足首の腫れが出なくなった。これまで慢性的に続いていた右下肢の筋緊張が取れ、全身のバランスも整ってきた。本人は「足首を気にせず全力でプレーできるのが嬉しい」と笑顔を見せた。
現在は、足首の不安定性や再発の不安はほとんどなく、社会人チームでの練習や試合を継続しながら、身体のメンテナンスとして定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
今回の右足首の捻挫癖は、繰り返しの捻挫によって靭帯が緩み、足関節の支持性が低下していたことが直接的な要因であるが、その背景には骨盤部の仙腸関節、特に腸骨の機能的変位が深く関与していたと考えられる。
仙腸関節の可動性が左右で不均衡になると、体重の軸がわずかに偏り、股関節・膝関節・足関節の連動が崩れる。特に腸骨の変位する方向によっては、股関節の内旋が助長され、結果としてつま先が内側を向く傾向が強まる。
この姿勢パターンは内反捻挫、すなわち足首を内側にひねる典型的な捻挫を誘発しやすい構造的環境を作り出していたと考えられる。
さらに本症例では、右短下肢が約2㎝と顕著な脚長差が確認されており、この左右差が骨盤の傾きと下肢の荷重バランスに大きな影響を与えていた。2㎝という差は、片方の靴を履かずにプレーしているのとほぼ同じ状態であり、身体全体が常に片側に傾いたまま動作していることを意味する。
その結果、右側への荷重が常に優位となり、右足首の外反・内反運動に不自然なストレスが繰り返し加わり、靭帯の弛緩を助長していた可能性が高い。
骨盤のアンバランスは下肢全体のアライメントを乱すだけでなく、足関節周囲の筋群の緊張パターンにも影響を及ぼす。特に外側支持に関与する腓骨筋群が常に引き伸ばされた状態で働くため、瞬間的な荷重変化への反応が遅れ、足首の内反方向へのブレが生じやすくなる。
また、仙腸関節や腰椎の機能低下は、下肢の固有感覚入力や運動制御を担う神経伝達にも影響を及ぼす。脳への感覚情報が正確に届かなくなることで、わずかな足首の傾きを検知する反射反応が遅れ、捻挫を防ぐタイミングを失うという悪循環が生まれていたと考えられる。
アジャストメントによって仙腸関節と腰椎の可動性が回復し、脚長差が改善されることで、両下肢への荷重配分が均等化した。神経伝達が正常化すると、足首からの感覚情報が脳に正確に伝わるようになり、歩行やキック動作中の足首の角度変化に対しても瞬時に安定化反射が働くようになる。それによって、再発を防ぐための動的安定性が再構築されたと考えられる。
本症例は、足首の捻挫癖を単に靭帯のゆるみや筋力低下といった局所的な問題として捉えるのではなく、骨盤・腰椎・下肢の連動性、さらには神経制御の観点から全身的に再評価する必要性を示したものである。
捻挫を繰り返す身体には必ずその背景となる構造的・神経的要因が存在する。カイロプラクティックケアによって神経の働きを回復させることが、構造と機能の両面から根本的な安定性を取り戻すうえで有効であることを示した、臨床的に非常に意義深い症例であった。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。