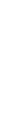症例紹介case introduction


インスリン注射を続けても血糖値が安定しない2型糖尿病
倦怠感が軽くなり、医師から「血糖値は安定していますね」と言われました!
カテゴリ:
消化器・呼吸器・肌などの症状でお悩みの方
40代男性
- 来院に至った経緯
-
20代の頃から営業職として外回りの多い生活を送っていた。朝は取引先への直行、昼は時間に追われてコンビニ弁当、夜は接待や会食が当たり前という日々だった。
若い頃は体力だけで乗り切ることができ、どんなに飲んでも翌日にはケロッとしていた。だが、気づけば運動をする習慣もなくなり、40代に入る頃には体重が10キロ以上増えていた。
本人も「少し太ったな」と自覚はしていたが、スーツのサイズを上げることでなんとなく誤魔化してきた。家族から「ちょっと太り過ぎじゃない?運動でもしたら」と声をかけられても、「仕事が忙しいから」と笑って済ませていた。
しかし数年前から、体の変化がはっきりと現れ始めた。午後になると強い眠気に襲われ、会議中に意識が遠のくような感覚があった。喉の渇きが取れず、デスクには常にペットボトルの水を置くようになった。夜はトイレのために何度も起き、そのたびに熟睡できない。朝は体が重く、鏡を見ると顔がむくみ、目の下のクマが濃くなっていた。
健康診断では毎年「血糖値が高め」と言われていたが、忙しさにかまけて再検査を受けずにいた。ある年、会社の定期健診でHbA1cが7.3%と指摘され、再検査の結果「2型糖尿病」と診断された。医師から「今の生活を続ければ、将来的にインスリン注射が必要になります」と言われた瞬間、頭の中が真っ白になった。
その後は食事制限と運動を始めたが、営業職の特性上、外食を避けるのは難しかった。昼食を軽く済ませても、午後になると強い空腹感とともに甘いものへの欲求が湧き、つい缶コーヒーやチョコレートに手を伸ばしてしまう。ストレスが溜まると反動で食べ過ぎてしまい、血糖値は乱高下を繰り返した。
医師からは「このままではコントロールできない」と言われ、ついにインスリン注射を開始することになった。最初は「注射だけは避けたかった」と落ち込んだが、やむを得ないと自分に言い聞かせ、なんとか生活を続けてきた。しかし、血糖値は思うように安定せず、倦怠感や集中力の低下、感情の波の大きさが続いた。
妻からも「最近イライラしやすくなった」と言われ、自分でもどうにかしたいという思いが強くなっていった。そんなとき、妻の友人の旦那さんが同じように2型糖尿病で、「ここに通ってからインスリン注射を手放せた」と当院を紹介してもらった。
「カイロプラクティックと糖尿病って関係ないでしょ?」と思っていたが、妻が「せっかく友達が紹介してくれたんだから1回行ってきて」と半ば強引に説得され、しぶしぶ当院に来院された。
【神奈川県茅ケ崎市から来院】
- 初診の状態
-
- 01
中部胸椎の明らかな可動域制限
- 02
隆椎周辺の強い浮腫感
- 03
脊柱起立筋全体の過緊張
- 01
- 経過と内容
-
初診時の状態では、下部頸椎や中部胸椎には明らかな可動域制限があった。体表温度検査では、下部頸椎・中部胸椎・下部腰椎に明らかに左右の温度の誤差が確認された。また隆椎周辺に強い浮腫が確認され、脊柱起立筋は全体的に過緊張の状態であった。
レントゲン評価では、椎間板をD1~D6という6段階で評価していく。腰の椎間板の段階は6段階中3段階の慢性的なD3レベルが確認された。首の椎間板の段階は6段階中4段階の慢性的なD4レベルが確認され、首の前弯カーブ(前カーブ)は消失してストレートネックとなっていた。
初期集中期の段階では週2回のケアを提示したが、営業職なので仕事の日は時間が読めないとのことで、無理のない範囲で週末の週1回のケアから開始した。
3週目(3回目のアジャストメント)には、朝のだるさがやや軽くなり、日中の眠気が少し減った。以前は昼食後に強い眠気に襲われていたが、仕事中の集中力がわずかに戻り始めた。夜中にトイレで何度も起きていたのが1〜2回に減り、睡眠の質が改善してきた。
7週目(7回目のアジャストメント)には、体の重さが軽減し、仕事後にも軽いウォーキングをする余裕が出てきた。呼吸が深くなり、慢性的な肩のこわばりが取れてきた。甘い缶コーヒーを飲む回数が減り、強い空腹感も和らいだ。食後のだるさが軽くなり、血糖値の乱高下が少なくなってきた。この段階でケアのペースを2週間に一度に広げることができた。
11週目(9回目のアジャストメント)には、感情の波が落ち着き、イライラや焦燥感が減ってきた。妻からも「最近顔色が良くなった」と言われ、家庭内でも穏やかに過ごせるようになった。病院の定期検診で医師からは、「だいぶ血糖値がコントロールできていますね」と言われるようになった。
17週目(12回目のアジャストメント)には、朝の目覚めがすっきりし、1日の体力の持続が感じられるようになった。血糖値の変動が安定し、倦怠感や眠気もほとんど出なくなった。病院での再検査ではHbA1cが6.1%に下がり、主治医から「血糖値は安定していますね。いまは寛解の状態です」と言われたとの報告があった。
現在は、血糖値は完全に安定し、寛解の状態を維持できている。寛解(かんかい)とは一時的に症状は落ち着いているが再発の可能性があるという意味であるため、再発防止と身体のメンテナンスとして定期的なカイロプラクティックケアを続けている。
- 考察
-
本症例の2型糖尿病は、交感神経の機能低下によって全身の代謝能力が低下し、膵臓や甲状腺などの内分泌系の働きが十分に発揮されなくなっていたことが背景にあると考えられる。糖代謝の調整は自律神経系の影響を強く受けており、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、エネルギー代謝の恒常性が失われていく。
交感神経は、血糖を一定に保つために肝臓や膵臓に働きかけ、インスリンやグルカゴンの分泌を微調整している。この働きが低下すると、血糖上昇に対する反応が鈍り、インスリンの作用が十分に発揮されない。結果として血糖値の変動が大きくなり、慢性的な倦怠感や集中力の低下を引き起こす。
検査では、下部頸椎・中部胸椎・下部腰椎に強い反応が確認された。下部頸椎は甲状腺と神経的に関係が深く、代謝全体の調整を担う重要な領域である。甲状腺ホルモンは細胞レベルでのエネルギー代謝を活性化させるため、この領域の神経伝達が乱れると、基礎代謝の低下やエネルギー生成の効率悪化を招く。
一方、中部胸椎は膵臓との神経的関連が強く、交感神経を介してインスリンやグルカゴンの分泌を制御している。ここでの神経的な干渉は、膵臓の反応性を鈍らせ、糖代謝リズムを乱す要因となる。特に慢性的なストレスや生活習慣の乱れによって交感神経の緊張が続くと、膵臓が過剰に負担を受け、インスリン分泌のリズムが不安定になる。
また、下部腰椎は骨盤部の構造的安定性に関わる領域であり、この部分の可動性が損なわれると、全身の姿勢保持や循環機能にも影響を及ぼす。腰部の筋緊張や可動性低下は、慢性的な疲労感や代謝効率の低下を助長し、結果として血糖コントロールの乱れを招くことがある。
カイロプラクティックケアによって下部頸椎・中部胸椎・下部腰椎の神経機能が回復し、自律神経系の伝達が正常化したことで、甲状腺と膵臓の協調が整い、エネルギー代謝のリズムが再び安定したことで血糖値の安定につながったと考えられる。
本症例は、糖尿病という代謝疾患の背景にも神経系の不均衡が存在することを示している。下部頸椎から胸腰部にかけての神経的機能を整えることで、全身の代謝恒常性が回復し、内分泌系のリズムが正常化していく。この神経機能の回復こそが、身体が本来持つ治癒力を取り戻すための鍵であり、サブラクセーション(根本原因)を取り除く意義を改めて示す症例であった。




ご予約・お問合せはお電話またはLINEから
- お電話での予約
- TEL:0466-21-9624
- LINEでの予約
- QRコードを読み取り、トーク画面から「予約希望」とご連絡ください。

執筆者前田 一真
神奈川県藤沢市出身。1972年に塩川満章D.C.が開院した銀座の塩川カイロプラクティックに内弟子として入る。塩川満章D.C.と塩川雅士D.C.に師事し、副院長まで務める。また日本で最も歴史あるカイロプラクティック学校シオカワスクールでは現役講師を務めており、後任の育成にも力を入れている。2023年5月に地元である藤沢の地で、カイロプラクティックの最前線である塩川カイロプラクティックで学んだ本物のカイロプラクティックを提供する院を実現するため、【前田カイロプラクティック藤沢院】を開院。
笑顔溢れ、心豊かに、幸せな毎日をサポートできるようにカイロプラクターとして尽力している。またシオカワグループの一員として、感謝・感動・希望に溢れる社会を目指している。